2019年02月10日
剣鉾・顔面カタログ 「嵯峨祭(愛宕神社・野宮神社) 龍鉾」

春の剣鉾祭りの最後を飾る嵯峨祭。
愛宕神社と野宮神社の両社の祭礼である。
剣鉾は五基の内、大門町守護の龍鉾。
毎年、釈迦堂門前の嵯峨豆腐・森嘉さんが鉾宿となり、
留守鉾が当家飾りされ、祭りが近づくと本鉾が立つ。
2009年07月02日
嵯峨祭・菊鉾へ表敬訪問
嵯峨祭・菊鉾の練習会への参加リポートを、
会長にいただいていたのを、完全に忘れていました。
会長!すみません。
遅ればせながら、記事UPさせていただきます。
■嵯峨祭・菊鉾表敬訪問リポート~~~~~~~~~~~~~~~~
5月17日夜は、鉾差し10名で嵐山の菊鉾の練習に表敬訪問して、
嵯峨鉾を持たしてもらいました。
以前から大半の方とは面識はありましたが、
正式に紹介していただきこれからの交流が深まりそうです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
菊鉾の練習場所、一条通大覚寺交差点の北東角にある広場で、
熱心に練習が繰り返されています。

京鉾の鉾差し10名が、代わり交替で嵯峨鉾を持たせてもらっています。

やはり、普段とは勝手が違うので、思うようにはいかないのです。
京鉾と差し方(振り方)は異なることで、棹を持つ右手の位置も違います。
京鉾の場合、右手は胸(みぞおち)から喉の辺りであるのに対して、
嵯峨鉾のそれは、頭よりも遥か上になります。
この手の位置については以前から注目しているのですが、
剣鉾が発達していった時代と共に、変化していったのではないかと考えています。
これについては、別項であらためて考えてみたいテーマです。

嵯峨鉾を持っての皆さんの感想を聞いたところ、
皆さん口を揃えて、"重い!"ということでした。
京鉾に比べて、体感プラス10kgはありそうやった、という声もあった程です。
全長で比べると、京鉾よりも嵯峨鉾の方が短いのですが、
嵯峨鉾の金飾りのボリュームは半端じゃないです。
鉾自体の重量は明らかに嵯峨鉾が重い様なのですが、
頭が重いことで、さらに重量感が増幅されているのかもしれません。
会長にいただいていたのを、完全に忘れていました。
会長!すみません。
遅ればせながら、記事UPさせていただきます。
■嵯峨祭・菊鉾表敬訪問リポート~~~~~~~~~~~~~~~~
5月17日夜は、鉾差し10名で嵐山の菊鉾の練習に表敬訪問して、
嵯峨鉾を持たしてもらいました。
以前から大半の方とは面識はありましたが、
正式に紹介していただきこれからの交流が深まりそうです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
菊鉾の練習場所、一条通大覚寺交差点の北東角にある広場で、
熱心に練習が繰り返されています。

京鉾の鉾差し10名が、代わり交替で嵯峨鉾を持たせてもらっています。

やはり、普段とは勝手が違うので、思うようにはいかないのです。
京鉾と差し方(振り方)は異なることで、棹を持つ右手の位置も違います。
京鉾の場合、右手は胸(みぞおち)から喉の辺りであるのに対して、
嵯峨鉾のそれは、頭よりも遥か上になります。
この手の位置については以前から注目しているのですが、
剣鉾が発達していった時代と共に、変化していったのではないかと考えています。
これについては、別項であらためて考えてみたいテーマです。

嵯峨鉾を持っての皆さんの感想を聞いたところ、
皆さん口を揃えて、"重い!"ということでした。
京鉾に比べて、体感プラス10kgはありそうやった、という声もあった程です。
全長で比べると、京鉾よりも嵯峨鉾の方が短いのですが、
嵯峨鉾の金飾りのボリュームは半端じゃないです。
鉾自体の重量は明らかに嵯峨鉾が重い様なのですが、
頭が重いことで、さらに重量感が増幅されているのかもしれません。
2009年05月23日
嵯峨祭2009・宵宮鉾飾り
野々宮神社と愛宕神社、両神社の祭礼・嵯峨祭が、
明日24日に還幸祭(おかえり)を迎えます。
本日は宵宮で、各町の鉾飾りを拝見してきました。
剣鉾は5基。
五つの地区で剣鉾が守護され、鉾差しの練習もそれぞれ独自で行われています。

剣鉾でも、一般的に”京鉾”(八大神社、西院春日神社など)と呼ばれる鉾の差し方とは異なり、
嵯峨祭独自の差し方で技術が伝承されています。
それは、京鉾の場合、鉾差しは上を見て鉾のバランスを保ち、
前後にマネキ(剣先)をしならせながら、
鈴(りん)は棹のナツメ(打金)に当てて鳴らしながら巡幸します。
それに対して嵯峨祭の鉾差しは、差し手は上を見ず、鉾を左右に振りながら、
鈴(りん)を棹に当て鳴らして巡幸してゆくのです。
また、嵯峨祭の剣鉾同士でも、差し方が異なっているいとのことでした。
このことから、同じ剣鉾といっても差し方や鉾の構造も異なっており、
それぞれの地域で、剣鉾が独自の進化を遂げてきたということが伺えます。
明日の還幸祭は、午前10時に剣鉾が嵯峨清凉寺前の御旅所を出発します。


◆牡丹鉾(天龍寺/龍門・角倉・造路町)の当家飾り

写真の鉾は、現在は稽古鉾として、巡幸には出ていませんが、
もともと本鉾であったもので、江戸時代の銘が残されています。



◆菊鉾(四区/小渕・井頭・西井頭町)









◆龍鉾(大門町)









嵯峨豆腐 森嘉さんの隣りで、当家飾りをされていました。




◆麒麟鉾(中院町)
慈眼堂(中院観音)のお堂で、当家飾りがされていました。














◆沢潟鉾(鳥居本町)







御旅所では、神輿が飾られていました。
野々宮大神と愛宕大神の神輿です。





嵯峨の里は、明日の本祭りを静かに待っていました。

明日24日に還幸祭(おかえり)を迎えます。
本日は宵宮で、各町の鉾飾りを拝見してきました。
剣鉾は5基。
五つの地区で剣鉾が守護され、鉾差しの練習もそれぞれ独自で行われています。

剣鉾でも、一般的に”京鉾”(八大神社、西院春日神社など)と呼ばれる鉾の差し方とは異なり、
嵯峨祭独自の差し方で技術が伝承されています。
それは、京鉾の場合、鉾差しは上を見て鉾のバランスを保ち、
前後にマネキ(剣先)をしならせながら、
鈴(りん)は棹のナツメ(打金)に当てて鳴らしながら巡幸します。
それに対して嵯峨祭の鉾差しは、差し手は上を見ず、鉾を左右に振りながら、
鈴(りん)を棹に当て鳴らして巡幸してゆくのです。
また、嵯峨祭の剣鉾同士でも、差し方が異なっているいとのことでした。
このことから、同じ剣鉾といっても差し方や鉾の構造も異なっており、
それぞれの地域で、剣鉾が独自の進化を遂げてきたということが伺えます。
明日の還幸祭は、午前10時に剣鉾が嵯峨清凉寺前の御旅所を出発します。


◆牡丹鉾(天龍寺/龍門・角倉・造路町)の当家飾り

写真の鉾は、現在は稽古鉾として、巡幸には出ていませんが、
もともと本鉾であったもので、江戸時代の銘が残されています。



◆菊鉾(四区/小渕・井頭・西井頭町)









◆龍鉾(大門町)









嵯峨豆腐 森嘉さんの隣りで、当家飾りをされていました。




◆麒麟鉾(中院町)
慈眼堂(中院観音)のお堂で、当家飾りがされていました。














◆沢潟鉾(鳥居本町)







御旅所では、神輿が飾られていました。
野々宮大神と愛宕大神の神輿です。





嵯峨の里は、明日の本祭りを静かに待っていました。

2009年05月23日
嵯峨祭2009・菊鉾研究会サイトリニューアル
2009春祭スケジュールでもお伝えしましたが、
愛宕神社・野々宮神社の祭礼「嵯峨祭 還幸祭」が、
5月24日に嵯峨清涼寺前の御旅所から大覚寺・嵐山全域にわたって行われます。


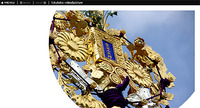
菊鉾に携っておられる方が運営されているサイト「菊鉾研究会」が、
近頃リニューアル致しました。
★そこで下記の通り、嬉しい「お知らせ」をされておられます。
►2009年の嵯峨祭の撮影写真(デジタル)・動画(DVテープ・DVD)を
提供していただいた方に、もれなく2009年のフォトシネマ(DVD)を差し上げます。
ご協力よろしくお願い申し上げます。
連絡先はサイト内のお問い合わせメールからお願いします。
どうぞご協力のほど、宜しくお願い致します。
☆嵯峨祭巡行予定・稚児行列、子ども御輿、剣鉾差し、愛宕・野々宮御輿巡行が行われます。
・神幸祭 5月17日 午前10:00
・還幸祭 5月24日 午前10:10
御旅所・・・・・鉾は10:10発 御輿は10:20発
大覚寺・・・・・鉾は12:40発 御輿は13:00発
嵐山嵐亭・・・鉾は15:10発 御輿は15:30発 御旅所着 17:00頃
愛宕神社・野々宮神社の祭礼「嵯峨祭 還幸祭」が、
5月24日に嵯峨清涼寺前の御旅所から大覚寺・嵐山全域にわたって行われます。


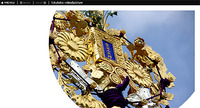
菊鉾に携っておられる方が運営されているサイト「菊鉾研究会」が、
近頃リニューアル致しました。
★そこで下記の通り、嬉しい「お知らせ」をされておられます。
►2009年の嵯峨祭の撮影写真(デジタル)・動画(DVテープ・DVD)を
提供していただいた方に、もれなく2009年のフォトシネマ(DVD)を差し上げます。
ご協力よろしくお願い申し上げます。
連絡先はサイト内のお問い合わせメールからお願いします。
どうぞご協力のほど、宜しくお願い致します。
☆嵯峨祭巡行予定・稚児行列、子ども御輿、剣鉾差し、愛宕・野々宮御輿巡行が行われます。
・神幸祭 5月17日 午前10:00
・還幸祭 5月24日 午前10:10
御旅所・・・・・鉾は10:10発 御輿は10:20発
大覚寺・・・・・鉾は12:40発 御輿は13:00発
嵐山嵐亭・・・鉾は15:10発 御輿は15:30発 御旅所着 17:00頃
2008年05月17日
『嵯峨祭の歩み』買いました!
昨日(16日)、京都新聞でも紹介されていた「嵯峨祭の歩み」を買ってきました。
嵯峨祭の成立起源から現在の嵯峨祭まで、筆者の推論を交えなが著された面白い本です。
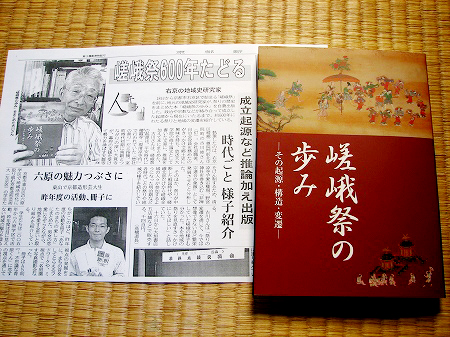
実際、「嵯峨祭」が"愛宕神社"と"野宮神社"の合同祭ということは、
よく語られる部分なんですが、
いざどんなお祭なのかを調べようとしても、
各神社のサイトでは、嵯峨祭に関する記述がほとんどなし。
これは、嵯峨祭が一般的によく言う"産土神の祭礼"という一本道の歴史を歩んできたのとは、
ちょっと違うのかなと、好奇心をくすぐるお祭なのです。
その部分の視野を拡げてくれる、面白い本です。

嬉しいのは、「嵯峨祭絵巻」の図録。
現在、嵯峨祭の剣鉾は5基だが、この絵巻には3基が描かれている。

今年の嵯峨祭は、5月18日がお出で(神幸祭)、25日がお還り(還幸祭)です。
もう各町では、練習鉾による練習がよりに行われています。
静かな嵯峨の里に、剣鉾の鈴の音が響いています。
嵯峨祭の成立起源から現在の嵯峨祭まで、筆者の推論を交えなが著された面白い本です。
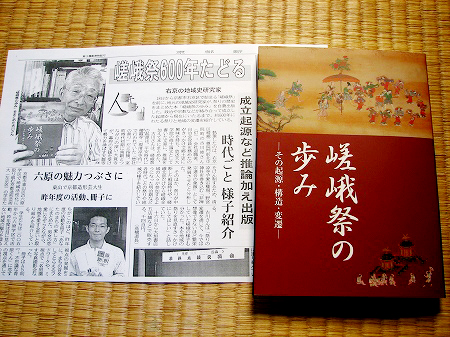
実際、「嵯峨祭」が"愛宕神社"と"野宮神社"の合同祭ということは、
よく語られる部分なんですが、
いざどんなお祭なのかを調べようとしても、
各神社のサイトでは、嵯峨祭に関する記述がほとんどなし。
これは、嵯峨祭が一般的によく言う"産土神の祭礼"という一本道の歴史を歩んできたのとは、
ちょっと違うのかなと、好奇心をくすぐるお祭なのです。
その部分の視野を拡げてくれる、面白い本です。

嬉しいのは、「嵯峨祭絵巻」の図録。
現在、嵯峨祭の剣鉾は5基だが、この絵巻には3基が描かれている。

今年の嵯峨祭は、5月18日がお出で(神幸祭)、25日がお還り(還幸祭)です。
もう各町では、練習鉾による練習がよりに行われています。
静かな嵯峨の里に、剣鉾の鈴の音が響いています。



