2009年12月11日
剣鉾祭による賑わい事業 11月23日
去る11月23日、祇園祭の原点といわれる神泉苑において、
神泉苑と京都二条城城下町振興会が中心となって、
剣鉾による”地域賑わい創出イベント”が行われました。

※左より「金鵄(きんし)鉾」「龍王鉾」「旭日(きょくじつ)鉾」のミニチュア子供剣鉾。








行事内容は、子供剣鉾を製作して、そのお披露目が行うというものです。
ここ神泉苑では、5月の神泉苑祭に3基の剣鉾/龍王鉾・金鵄鉾・旭日鉾(日章鉾)が
お飾りされます。そのミニチュア版を作られたようです。
将来的には66本まで製作を考えておられるとのことです。




また、神泉苑境内にお祀りされている”矢劔大明神”と”増運辯財天”の御火焚祭も執り行われ、
よかろう太鼓の奉納、秋の収穫・物産展なんかも開催されたようです。
私が行った時には、太鼓奉納も物産展も終わっていました。
僅かに、お火焚きの火が残っているだけでした。
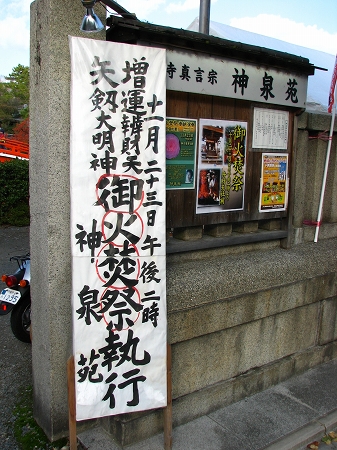

神泉苑の紅葉がきれいに色付いて、行く秋を惜しんでいるようでした。
しばし、境内の紅葉を眺めていました。
この投光器がなかったら・・・
↓


だんだん奥の一点に迫ってゆきます。すると何かが見えてきました。




なんと、五位鷺が池端の木の枝に留まっていました。
■ 剣鉾祭による賑わい事業
■ 神泉苑祭2009
■ 神泉苑祭 2007年5月3日
神泉苑と京都二条城城下町振興会が中心となって、
剣鉾による”地域賑わい創出イベント”が行われました。

※左より「金鵄(きんし)鉾」「龍王鉾」「旭日(きょくじつ)鉾」のミニチュア子供剣鉾。








行事内容は、子供剣鉾を製作して、そのお披露目が行うというものです。
ここ神泉苑では、5月の神泉苑祭に3基の剣鉾/龍王鉾・金鵄鉾・旭日鉾(日章鉾)が
お飾りされます。そのミニチュア版を作られたようです。
将来的には66本まで製作を考えておられるとのことです。




また、神泉苑境内にお祀りされている”矢劔大明神”と”増運辯財天”の御火焚祭も執り行われ、
よかろう太鼓の奉納、秋の収穫・物産展なんかも開催されたようです。
私が行った時には、太鼓奉納も物産展も終わっていました。
僅かに、お火焚きの火が残っているだけでした。
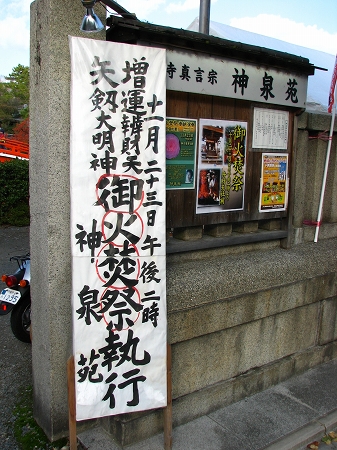

神泉苑の紅葉がきれいに色付いて、行く秋を惜しんでいるようでした。
しばし、境内の紅葉を眺めていました。
この投光器がなかったら・・・
↓


だんだん奥の一点に迫ってゆきます。すると何かが見えてきました。




なんと、五位鷺が池端の木の枝に留まっていました。
■ 剣鉾祭による賑わい事業
■ 神泉苑祭2009
■ 神泉苑祭 2007年5月3日
2009年05月02日
神泉苑祭2009
神泉苑祭が始まりました。
5月4日まで、いろんな行事が盛りだくさんです。
お祭も楽しいですが、
ここではやっぱり”神泉苑狂言”が公演されます。
これは、春祭りの中でも、必見の行事です。
基本的に無料で鑑賞公開されていますが、
志納BOXをご用意されていますので、ぜひ、志しをお願いします。
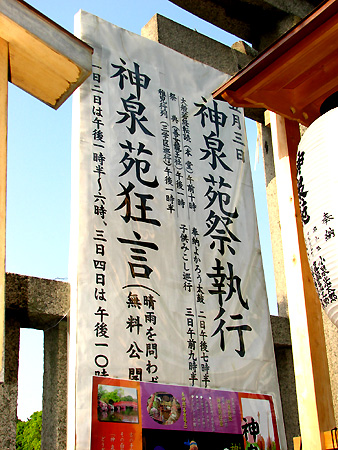

神泉苑祭には、3基の剣鉾が守護されています。
名称は、
中が◆龍王鉾(りゅうおうぼこ)
左が◆金鵄鉾(きんしぼこ)
右が◆旭日鉾(きょくじつぼこ)
右の剣鉾は、日章鉾(にっしょうぼこ)という情報もあるのですが、
昭和50年ころにお聞きした時に、旭日鉾という鉾名が出ていましたので、
ここでは、旭日鉾としておきます。




剣鉾の状態は、非常に痛みが激しく、鉾差しには耐えられない状態です。
長柄も漆塗りは剥がれ落ちてしまっています。
製作年代は、箱書きや銘を確認していないので不明ですが、
金鵄鉾と旭日鉾は、明らかに近代以降になるでしょう。
意匠が、勲章から引用したものになっていますからね。
田中緑紅著(1969発行)「ふるさとの祭と行事」の神泉苑祭の項に、
昭和6年5月1日の祭礼写真が掲載されています。
その部分の解説文によると、一時中絶せられていた神泉苑祭が、
明治30年頃から再興されて、9月1日だった祭礼日も5月1日と改めた、
ということが書かれていました。
そのことから、剣鉾の製作年代は、おそらく再興時の明治30年頃ということが推測されます。
さらに当時の祭礼の様子が書かれています。
神輿は三条台若中によって舁かれていた、とありました。
”三条台若中”は、現在あの祇園祭の中御座(素戔嗚尊)を舁いている三若神輿会のことです。
巡幸列については、
太鼓-榊-舞獅子-神馬-稚児-剣鉾-神輿と続き、
楽人・神官が神輿の先に歩いたとあります。
特に面白いのは、住職(僧侶)が腕車に乗って供奉していたと書かれていました。
これは、神泉苑が東寺真言宗の寺院であるということによるもので、
神泉苑内の”善女龍王社”の祭礼が「神泉苑祭」ということなのです。
これは推測なのですが、明治30年頃に再興するまでの一時期中絶していたのも、
明治政府による廃仏毀釈・神仏分離政策が、
神泉苑祭の継続を不可能にしたのだと考えられます。
明治もこの頃になると、少しは神仏分離の嵐は緩くなってきたのでしょうか。





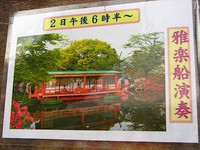

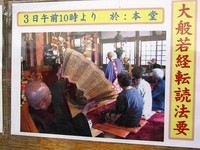
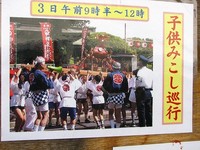



神泉苑狂言は、壬生狂言の流れを汲んでいます。
壬生狂言とおなじようにセリフのない無言劇です。
演者の声は聞こえませんが、
ガンデンデン…ガンデンデン…と鉦と太鼓・笛の音だけが神泉苑の境内に響いてきます。

奥をのぞくと、狂言がちらほら見えてきます。
ちょっと望遠でのぞき見・・・

狂言つながりで、こんなポスターもあります。
”千本えんま堂狂言”5月1日~4日までの公演です。
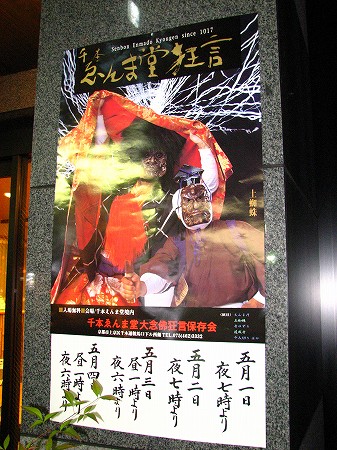
※以前の神泉苑祭記事です。
・「神泉苑祭2007 5月3日」
・「神泉苑祭2006」
5月4日まで、いろんな行事が盛りだくさんです。
お祭も楽しいですが、
ここではやっぱり”神泉苑狂言”が公演されます。
これは、春祭りの中でも、必見の行事です。
基本的に無料で鑑賞公開されていますが、
志納BOXをご用意されていますので、ぜひ、志しをお願いします。
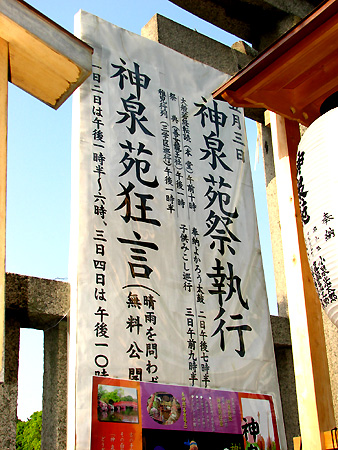

神泉苑祭には、3基の剣鉾が守護されています。
名称は、
中が◆龍王鉾(りゅうおうぼこ)
左が◆金鵄鉾(きんしぼこ)
右が◆旭日鉾(きょくじつぼこ)
右の剣鉾は、日章鉾(にっしょうぼこ)という情報もあるのですが、
昭和50年ころにお聞きした時に、旭日鉾という鉾名が出ていましたので、
ここでは、旭日鉾としておきます。




剣鉾の状態は、非常に痛みが激しく、鉾差しには耐えられない状態です。
長柄も漆塗りは剥がれ落ちてしまっています。
製作年代は、箱書きや銘を確認していないので不明ですが、
金鵄鉾と旭日鉾は、明らかに近代以降になるでしょう。
意匠が、勲章から引用したものになっていますからね。
田中緑紅著(1969発行)「ふるさとの祭と行事」の神泉苑祭の項に、
昭和6年5月1日の祭礼写真が掲載されています。
その部分の解説文によると、一時中絶せられていた神泉苑祭が、
明治30年頃から再興されて、9月1日だった祭礼日も5月1日と改めた、
ということが書かれていました。
そのことから、剣鉾の製作年代は、おそらく再興時の明治30年頃ということが推測されます。
さらに当時の祭礼の様子が書かれています。
神輿は三条台若中によって舁かれていた、とありました。
”三条台若中”は、現在あの祇園祭の中御座(素戔嗚尊)を舁いている三若神輿会のことです。
巡幸列については、
太鼓-榊-舞獅子-神馬-稚児-剣鉾-神輿と続き、
楽人・神官が神輿の先に歩いたとあります。
特に面白いのは、住職(僧侶)が腕車に乗って供奉していたと書かれていました。
これは、神泉苑が東寺真言宗の寺院であるということによるもので、
神泉苑内の”善女龍王社”の祭礼が「神泉苑祭」ということなのです。
これは推測なのですが、明治30年頃に再興するまでの一時期中絶していたのも、
明治政府による廃仏毀釈・神仏分離政策が、
神泉苑祭の継続を不可能にしたのだと考えられます。
明治もこの頃になると、少しは神仏分離の嵐は緩くなってきたのでしょうか。





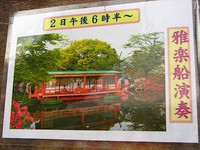

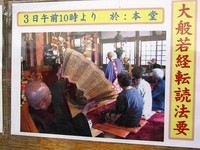
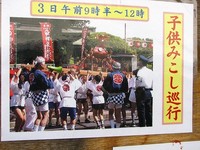



神泉苑狂言は、壬生狂言の流れを汲んでいます。
壬生狂言とおなじようにセリフのない無言劇です。
演者の声は聞こえませんが、
ガンデンデン…ガンデンデン…と鉦と太鼓・笛の音だけが神泉苑の境内に響いてきます。

奥をのぞくと、狂言がちらほら見えてきます。
ちょっと望遠でのぞき見・・・

狂言つながりで、こんなポスターもあります。
”千本えんま堂狂言”5月1日~4日までの公演です。
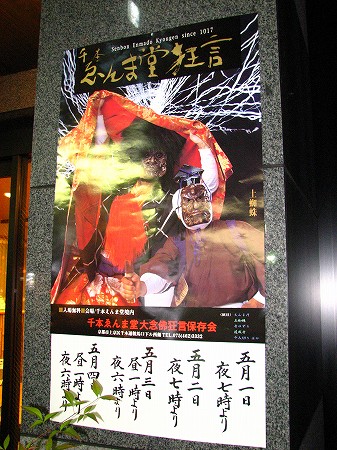
※以前の神泉苑祭記事です。
・「神泉苑祭2007 5月3日」
・「神泉苑祭2006」
2007年05月07日
神泉苑祭 5月3日
神泉苑そのものは、現在真言宗東寺に属する寺院で、
神泉苑祭は、その神泉苑内に祀られている「善女龍王社」の祭礼である。
明治初頭の神仏分離により、その姿は変貌したであろうが、
神仏習合の様子を窺い知ることができる。
この神泉苑祭の行事内容にも、本堂での大般若経六百巻の転読法要が行われたりする。

氏子区域は3学区52ヶ町ほどのものであるが、
お稚児さんのお練り・子供みこし・よかろう太鼓・大般若経転読・神泉苑狂言などなど、
内容は様々で、非常に見所の多い祭である。






剣鉾は、龍王鉾・金鵄鉾・旭日鉾の3基である。




◆龍王鉾(りゅうおうぼこ)


◆金鵄鉾(きんしぼこ)

◆旭日鉾(きょくじつぼこ)



5月1日~4日まで、京都市登録 無形民俗文化財「神泉苑狂言」が、
神泉苑の東端にある狂言堂で執り行われる。
壬生狂言の流れを汲み、演者は全て面をつけ、
完全に無言で金鼓・太鼓・笛のはやしに合わせて演じるのである。
演目は30種あり、日替わりで順番に演じていくようである。
志納金を納めると、観覧することが出来る。



その日その日の演目は、狂言堂上り口のところに掲示されている。
神泉苑狂言の公演中に授かる厄除けのお守りです。
演目「土蜘蛛」で、土蜘蛛が撒く糸玉が入っている。
「くものす」は財布に入れていると、福を招くとの言い伝えがある。
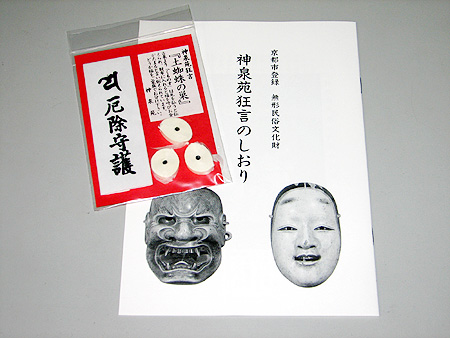

■神泉苑(善女龍王社)
◆御祭神…善女龍王
◆御鎮座地…京都市中京区御池通神泉苑町東入る門前町166
神泉苑祭は、その神泉苑内に祀られている「善女龍王社」の祭礼である。
明治初頭の神仏分離により、その姿は変貌したであろうが、
神仏習合の様子を窺い知ることができる。
この神泉苑祭の行事内容にも、本堂での大般若経六百巻の転読法要が行われたりする。

氏子区域は3学区52ヶ町ほどのものであるが、
お稚児さんのお練り・子供みこし・よかろう太鼓・大般若経転読・神泉苑狂言などなど、
内容は様々で、非常に見所の多い祭である。






剣鉾は、龍王鉾・金鵄鉾・旭日鉾の3基である。




◆龍王鉾(りゅうおうぼこ)


◆金鵄鉾(きんしぼこ)

◆旭日鉾(きょくじつぼこ)



5月1日~4日まで、京都市登録 無形民俗文化財「神泉苑狂言」が、
神泉苑の東端にある狂言堂で執り行われる。
壬生狂言の流れを汲み、演者は全て面をつけ、
完全に無言で金鼓・太鼓・笛のはやしに合わせて演じるのである。
演目は30種あり、日替わりで順番に演じていくようである。
志納金を納めると、観覧することが出来る。



その日その日の演目は、狂言堂上り口のところに掲示されている。
神泉苑狂言の公演中に授かる厄除けのお守りです。
演目「土蜘蛛」で、土蜘蛛が撒く糸玉が入っている。
「くものす」は財布に入れていると、福を招くとの言い伝えがある。
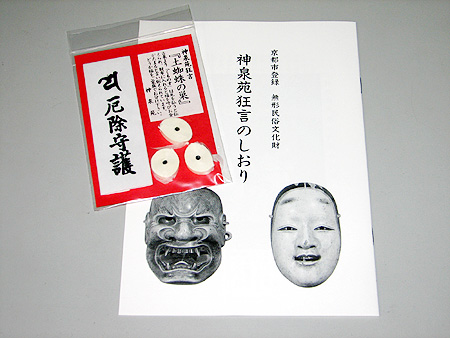

■神泉苑(善女龍王社)
◆御祭神…善女龍王
◆御鎮座地…京都市中京区御池通神泉苑町東入る門前町166
2006年04月29日
神泉苑祭
二条城の南、神泉苑に祀られた「善女龍王社」のお祭です。  地図はこちら
地図はこちら
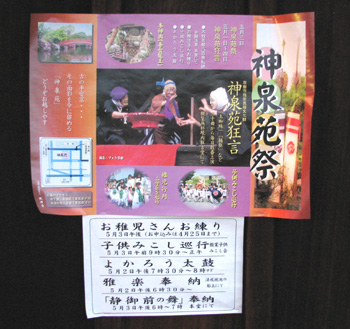
お祭りは、5月3日。
この日をはさんで、様々な行事が執り行われます。

剣鉾は、三本。
中央の龍王鉾・右側の旭日鉾・左側の金鵄鉾。
龍王鉾は、剣鉾伝統の意匠を具えているのに対し、旭日鉾・金鵄鉾は、名称からもわかるとおり、軍国色の濃い意匠と名称になっています。
おそらく、昭和期に製作されたものなのでしょう。
この神泉苑は、
平安京が造られた時に大内裏の南東に建設された苑池で、
当時は、現在の10倍以上の広さを持ち、
古から、この神泉苑は、あらゆる泉や河川が枯れようとも、
豊かな水をたたえて、枯れることは無かったそうです。


この池は、御池通の名前の由来にもなっています。

有名なお話に、天長元年(824年)・干ばつが続き、
時の天皇は、東寺の空海と西寺の守敏に神泉苑で雨乞いの法力を競わせ、空海が雨を降らせたことから、
その後、東寺はさらに隆盛を極め、現在に至っています。
この縁から、神泉苑は現在、東寺真言宗の寺院となっています。
この神泉苑祭で、是非観ていただきたいのは、
あの有名な壬生狂言の流れをくむ、神泉苑狂言です。
以前は、観覧料は無料でしたが、現在は志納ということで、心付けを収めるということになっているようです。

公演スケジュールは、こんな感じです。

もう一つ、名物というか、こんなのはどうですか。

歳徳神の祠があります。
よく観てください。台座が丸いでしょ。
それは、毎年、祠の向きが変わるからなんです。
その歳々の恵方に向いて、お参りができるようにクルクル回ります。
因みに、今年の恵方は南南東とのこと。

本堂での、般若心経の豪快な転読も見ものですぞ。

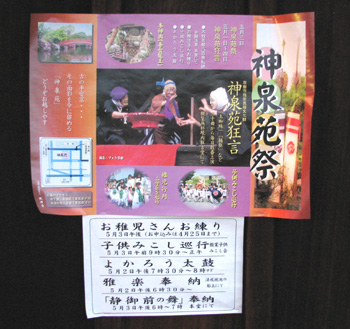
お祭りは、5月3日。
この日をはさんで、様々な行事が執り行われます。

剣鉾は、三本。

中央の龍王鉾・右側の旭日鉾・左側の金鵄鉾。
龍王鉾は、剣鉾伝統の意匠を具えているのに対し、旭日鉾・金鵄鉾は、名称からもわかるとおり、軍国色の濃い意匠と名称になっています。
おそらく、昭和期に製作されたものなのでしょう。
この神泉苑は、
平安京が造られた時に大内裏の南東に建設された苑池で、
当時は、現在の10倍以上の広さを持ち、
古から、この神泉苑は、あらゆる泉や河川が枯れようとも、
豊かな水をたたえて、枯れることは無かったそうです。


この池は、御池通の名前の由来にもなっています。

有名なお話に、天長元年(824年)・干ばつが続き、
時の天皇は、東寺の空海と西寺の守敏に神泉苑で雨乞いの法力を競わせ、空海が雨を降らせたことから、
その後、東寺はさらに隆盛を極め、現在に至っています。
この縁から、神泉苑は現在、東寺真言宗の寺院となっています。
この神泉苑祭で、是非観ていただきたいのは、
あの有名な壬生狂言の流れをくむ、神泉苑狂言です。
以前は、観覧料は無料でしたが、現在は志納ということで、心付けを収めるということになっているようです。

公演スケジュールは、こんな感じです。

もう一つ、名物というか、こんなのはどうですか。

歳徳神の祠があります。
よく観てください。台座が丸いでしょ。
それは、毎年、祠の向きが変わるからなんです。
その歳々の恵方に向いて、お参りができるようにクルクル回ります。
因みに、今年の恵方は南南東とのこと。

本堂での、般若心経の豪快な転読も見ものですぞ。




